0からのtoeicパート1対策
英語を全くの0から始める場合にまず最初に取り組むことになるのがパート1です。
全体のうち僅か6問となることから費用対効果が薄いと考えられるパート1ですが、0から始めた人に取っては文法や語彙について学べることが多いパートとなるのでしっかりとやることをお勧めします。
土台を作ってあげればこの後のパート2やリーディングなどにも効いてくる侮れないパートです。
おすすめの取り組み方を学習初期の方に向けて紹介します。
パート1では時制と語彙が鍵
パート1ですが、そのほとんどが語彙と時制による表現で構成されています。
そのため、語彙と時制の表現による差を理解することが得点に繋がります。
パート1のこの基礎的な表現の理解はそのままリスニングやリーディングで使われるため、パート1の理解を深めることで他パートの理解が深まります。
そのため、個人的には全体の6問程度しか出ないから取り組まないのではなく、学習初期程積極的に取り組んでいくべきパートかなと思います。
パート1の意外な落とし穴
パート1ですが、総問題数は200問中の僅か6問とあまりにも少ない出題数が目立ちます。
ですがリスニング試験は必ずこのパートから始まり、パート1の出来や回答の精度(自信をもって答えられるか)によってはパート2以降の試験に大きなメンタル的なダメージを追います。
短距離走でスタートの切り方が大事なように、パート1のスタートは試験全体の影響に左右する重要なものとなります。
私自身パート1で2問ぐらい分からない時があり、パート2やリスニングに影響を与えてしまったことがあります。
相性の有無は絶対にありますが、ペースを崩されないためにもパート1対策はある程度しておく方が良いと思います。
パート1の知識が深まる学習方法
ではパート1はどのように勉強していくのが良いのでしょうか?パート1のカギは語彙と時制という話をしました。
これから英語学習を進めていく方たちは何千という単語に遭遇することになりますが、知らぬ音やイメージを音と結びつけてもなかなかに定着することはありません。
例として我々になじみの日本語でこれを表現するとリンゴと言われれば言葉と一緒に赤い丸いリンゴが浮かびませんか?
ではビーチバレーはどうでしょうか?なんとなく浜辺でラリーなり打ち合いをしている人たちの姿が浮かびませんか?
では私の好きな領域でオオルリオサムシと言われたらどうでしょう? これは昆虫の中でもややマイナー寄りな虫の名前です。
恐らくこの記事に来た方の中で姿がイメージとして結びついている方はいないでしょう。
そう、日本語では当たり前にやっている単語とイメージの連結が、なぜか英語学習になると単語だけ学ぼうとする人が出てくるのです。
リスニングでは音と共にその語彙のイメージが付いてくることはとても重要です。
僅か数秒で流れる音声の中でこの単語は~こうだから~なんて考えている余裕はありませんよね。
そのためにもその語彙が持つイメージを覚える必要があります。
ではどうするか?それはその語彙をグーグルやヤフーの検索で調べて画像検索してみるのです。
英単語の画像検索のすすめ
この前ベランダとテラスとバルコニーの違いを目にしました。これらは英語の用語ですが、調べてみると使い分ける基準があります。
調べてみてください。面白いですよ。軽く述べるとベランダは屋根があり、バルコニーには屋根がありません。同様にデッキやテラスなどの違いも画像で調べると一目瞭然です。
こうして意味の違いをイメージとつなげるよう日々の学習でイメージすると、パート1だけでなく、英語学習を通じて語彙のイメージが蓄積されていきます。
私は初期に単語のみを調べてこの画像検索をしてこなかったため、また出会った単語をわざわざ画像検索する二度手間を踏みましたが、この記事を見た方は大丈夫ですね。
身近なものの状態でアウトプット
パート1の勉強方法の王道として、時制の部分においては身近にあるものや目の前にある状況などを表現してみることをおすすめします。
be doneの受動態なのかbeing doneで今されているのか be going toなのかhave doneなのか
こうした時制の違いは受動的に問題を見てやるだけでなく、積極的にアウトプットを交えることでこの場合どの表現を合わせるのが適当なんだ?と多くの疑問が湧いてくるはずです。
例えばコップを動かすという動作。
実際に持って動かす最中はbe going toですが、動作主がコップなのか私なのかという差が有りますよね。動かしているならbe going to 動かされているなら being done
では動かし終わっている場面ならどうでしょうか? have done ですよね。
こんな感じで目の前で状態を動かしてこれはどう表現するかというのをやってみるのです。
そうした目の前のものを自分で問題化していくと、同じような表現パターンにぶつかる時にこんな感じで表現されるかもなという勘が働きます。
一種の先読みのように機能するので、解きやすくなってきますよ。

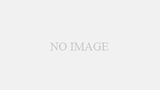
コメント