toeicの点数を上げるならば問題を解きまくれ
toeicの点数を効率よく上げたいと思って色々な問題集に手を出し、次から次に教材を乗り換えていませんか?
教材は解くのが大事だから間違えた問題だけ見直して次の問題へ!というのは学習初期のあるあるかと思います。
この問題集を解きまくるという視点は勘違いされやすいポイントです。
正しくは同じ問題集を解きまくれという意味なので、今回は同じ問題をひたすら解く必要性と問題集をころころ変えてはいけない理由も紹介します。
そして点数を上げるための復習と繰り返しの方法を紹介します。
問題集を解きまくれの罠
toeicにおいては出題傾向にはパターンがあることから、その傾向に慣れるためにたくさん問題を解くという方法があります。
これは見方によっては正しく、間違いでもあります。
正しくは解いた問題を繰り返し解く中でパターンに慣れ、それの積み上げで傾向を読めるようになるというのが学習の流れです。
英語においては精読と言って文構造や単語、発音などなどの要素をしっかりと理解して復習を長期間繰り返し、解いた内容を無意識で理解できるようにしていけるのが理想です。
そのため、1つの摸試を解いて終わりではなく、むしろ解いてからが学ぶ上では大切なのです。
教材コレクターになるな
これの逆としては問題集が解き終わったから間違えた問題や正答の良し悪しだけを見て、別の教材に手を付けてしまうものが挙げられます。
これは教材にお金だけをかけて身につくものもなく、時間だけを浪費してしまう良くないパターンの代表格です。
日常で考えてみると分かりやすいと思いますが、例えば新人として入った会社にて業務をこなしていくと様々な分からない箇所が出てきますよね。
その際には上司や同僚などに分からない場所を聞いて、こういう時はこのやり方で対処すればいいんだなと学んでいきますよね。
趣味などにおいても同様です。例えば不味いお店に入ってしまったならば次からはちょっとレビューを参考にしてみようかななど手を打ちますよね。
人は失敗をした後に物事を学びます。
教材を解いて復習をしないことは、一度したミスを放置していることと同義であり、別の教材で同じような問題が出た時に再び間違えてしまうことに繋がります。
そうすると点数の停滞に繋がってしまうのです。
皆様も教材コレクターにはならないよう気を付けてください。
身につく復習方法、精読とは
では解いた問題集はどのように復習していけばよいのでしょうか
まず結論としては解いて精読した問題を音読し続ける。これだけです。
字面だと簡単そうに聞こえますが、しっかりやるのは難しかったりします。目指すところは人にその教材の問題を説明できる所までです。
精読には色々な手法があるのであくまで私がやっているやり方です。
まず正誤に関係なく問題は一つずつ見ていきます。toeicの問題においては4択であるため、正解できたとしても偶然によるものがあるためです。
回答の根拠を自身で答え、それが教材側の正答となる理由と同じかを検討します。
間違えてしまった問題は自身の理由と回答根拠のズレを認識し、どのように思考すれば正解となったのかを確認します。
間違えたところだけやるのではなく全ての問題をやるのがポイントですね。
また、問題文にある分からない単語や表現、使われている文法などが自分の認識とズレが無いのかというのも確認していきます。
単語をチェックするときは発音にも注意し、英語に特有な音の繋がりも変化をちゃんと調べます。
これをしっかりこなしていくと各パートをこなすだけでも相当大変であることが分かるかと思います。
ですがこれはパート対策という枠組みでなく、全部のパートに共通して使える復習方法なのでやり方だけ覚えてしまえばあとは各パートの問題を同様のやり方で積み上げていくだけです。
もちろんリスニングにはリスニングの、リーディングにはリーディングのテクニックもあるのですが、この記事では全体に使える方法を紹介しておきます。
こうした英文の構造を理解するのが精読と呼ばれる作業です。復習の根幹となる最重要作業なのですが、精読をして終わってはいけません。
自分が分解し細部を理解した文章を無意識に理解させるため、音読をひたすら繰り返す必要があります。
音読はもう飽きるまでです。飽きてもやるべきです。舌の筋肉が動かなくなるくらいまでやりましょう。
音読は即効性は無いものの英語のあらゆるパートあらゆる発声、あらゆる理解の土台となるスーパーメソッドです。
隙間時間やふとした時に音読をしていいぐらい万能な勉強なのですが、いかんせん長期間かけてじわじわと効いてくるため、その効果を認識しにくいのが悩みどころですね。
精読したものを読む
音読についてですが、最初の内は自分が精読において分解した要素を意識しながら丁寧に声に出していきます。
発音記号もそうですし音の繋がりはしっかりと音源を聞いて真似するようにします。
単語や語法などはパーツとしてなぜその意味になるかも止めて確認し、それらを何回も繰り返しながら一文ずつ音読していきます。
それを各文で繰り返します。
リンゴと文字を見たら丸く赤いものが浮かびますよね。staplerと聞くとどうでしょうか?
これに限らず復習教材の単語が自動でイメージできるぐらい読んでいきます。
その後文として全体を音読していきます。
私はtoeicを本腰入れてやっていた時は7~8時間勉強していました。
当時は無職だったのですが、1つの摸試はおおよそ3週間ぐらい回答から復習まででやっていましたね。
それぐらいやったからか集中的にやっていた期間は750位まであっという間でした。全くの0から初めて4~5か月でこの辺りまで来たので、十分効果的だと思います。
何よりどのパートもやることのベースが同じなのがいいですよね。
600までの参考教材数
実際最初の目標となる600点や700点ぐらいまで全くの0から始めた場合にはどれぐらいの教材がかかるのか気になりますよね。
私を例にすると私は英語苦手、大学受験でもほとんど勉強してないレベルから始めましたが、600点までは約3か月半ぐらいでしょうか。
これまでに使ったのは思考の摸試(摸試3回分600問)、特急シリーズのパート3,41冊、英語耳、後はtoeic学習開始前にduo3.0をやっていたぐらいですね。
600までは中学の領域がそれなりに理解できれば登れるという感覚で、それは摸試を今回の方法でしっかりやっていき、分からない箇所を肉付けしていけば十分間に合うように感じます。
個人的には通読とかも不要かなという立場で、とにかく出会った分からない表現、文法、単語、発音を徹底的に音読で繰り返していくのが効果的だと思います。
問題を解きまくりそれで扱った教材を増やしていけばおのずと分かる範囲が増えていき、同じパターンに遭遇しても解けるようになっていきます。
教材はより少なく、しかし繰り返すことでより多く吸収していくのが安くかつ効率的な勉強になると思いますね。

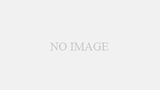
コメント