伸び悩むtoeicの点数、勉強は無駄なのか?
toeicを続けていると試験を受けても手ごたえがなく、停滞していることを自覚するタイミングが来ます。

勉強しても意味が無いのかな、英語の才能が無くてここから上には行けないのかな?と心配になるこの停滞期ですが、いわゆるプラトーといって英語に限らずある程度物事の知識がたまるとみられる停滞現象です。
つまりプラトーの存在を知っておけば焦ること無くすべき勉強の継続ができます。
この記事では停滞期としてのプラトーと収穫逓減の法則を通じて英語学習における停滞と対策を紹介します。
プラトーとは?
プラトーは筋トレでよく使われる用語です。
これまで順調に伸びてきた重量がある時を境に停滞し、筋トレをどれだけしても伸びていないように感じてしまう現象です。

期間はケースにより、異なり2週間程度のこともあれば1か月2か月程度かかるものもあります。
プラトーの突破には色々な要素がありますが、突破できると以前よりぐんっと重量が増える様子が見られます。
この話を聞いて英語でも当てはまると思いませんか?
英語学習の初期は単語や文法発音などなど吸収する要素の余地が多いのでその分成長も早まります。
およそ600点くらいまでは右肩上がりで時間をかける程伸びていくのを体感できるはずです。

ところがあるところから点数が停滞したり下がる場合があります。
ここで停滞期のことを知らず勉強をやめてしまう人と停滞期が来たかと勉強を続ける人に分かれます。
そして勉強を続けていれば停滞期を突破し、リスニングや構文が急に見やすくなるいわゆるブレイクスルーに繋がります。
このようにプラトーはジャンルが違えども同じ性質が見られます。重要なのは事前に停滞期が来るということを知っておくことです。
プラトー打破には2つの選択肢
個人的な筋トレと英語学習両方の経験からプラトーの打破には2つの要素が必要になると考えられます。
まず一つが同じやり方でも勉強量を継続することで勝手に打破できる場合です。
この場合は単純に知識の蓄積量が原因となっていることが多く、一定の期間ののち学習方法などを変えなくても突破できることが多いです。

一方で同じやり方をしていてもプラトーが打破できない場合があります。
この場合には違う勉強方法や違うパートの勉強(リスニングパートを伸ばすためにリーディングパートをやるなど)を使うなど勉強へのアプローチを変えて刺激を変えてやる必要があります。
例えば有効だと感じたのは「音読だけしていた時間のうち半分を暗唱に充ててみる。」
今一度文法書を読み直して分かった気になってしまっているところが無いか確認してみるなどがあくまで例としてですが挙げられます。
このプラトーの場合には何かがボトルネック(あしかせ)となっている可能性があり、それにより他の要素に影響が出ているというものです。
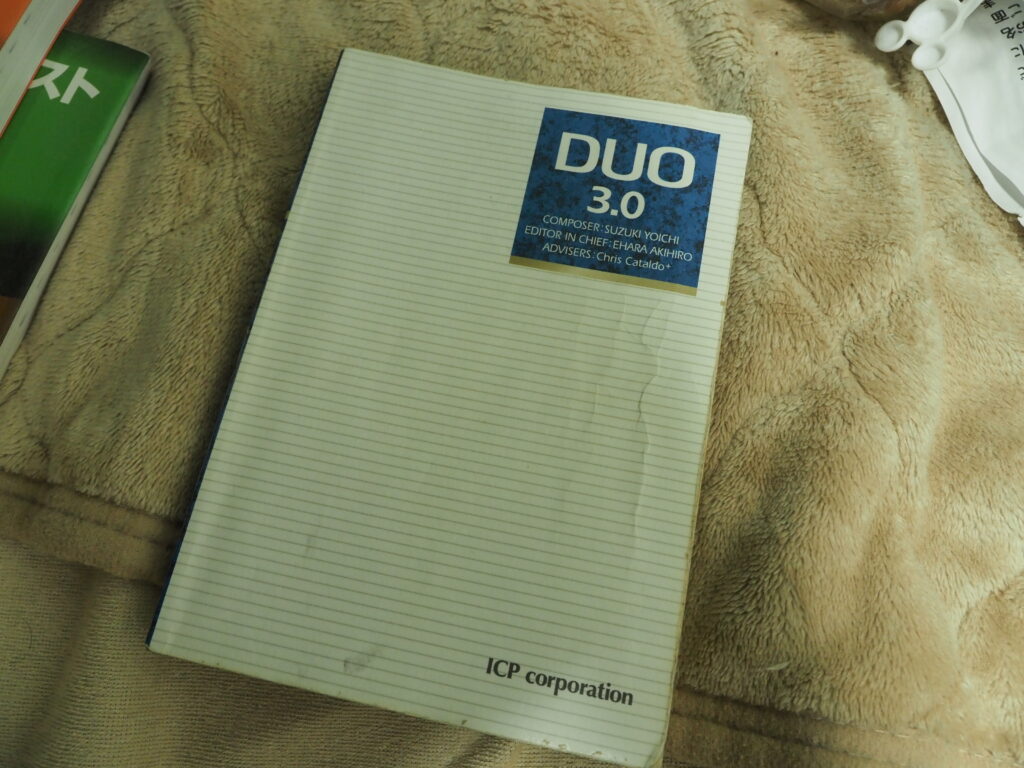
分かりやすく言うと同じ教材(語彙数1500とする)で音読を続けていくと基礎的な文法やその教材に出てくる単語などの知識はバッチリつきますが、その教材外の単語などが見に付きません。
600点に必要と言われる語彙数は4000~5000程度と言われていますので、その教材を続けて基礎を鍛えていっても語彙数がボトルネックになることが分かりますよね。
この場合には語彙数を増やそうとすればよいと分かりますが、実際にプラトーの最中にいると何が問題なのかはなかなか分からないものです。
toeicにおいてプラトーを感じやすい人
toeicにおいて停滞しやすい人というのはいます。それはリスニングが苦手な人です。
私がそうだったのでよく分かるのですが、toeicはリスニングが得意かどうかで点数の伸び具合が大きく変わります。
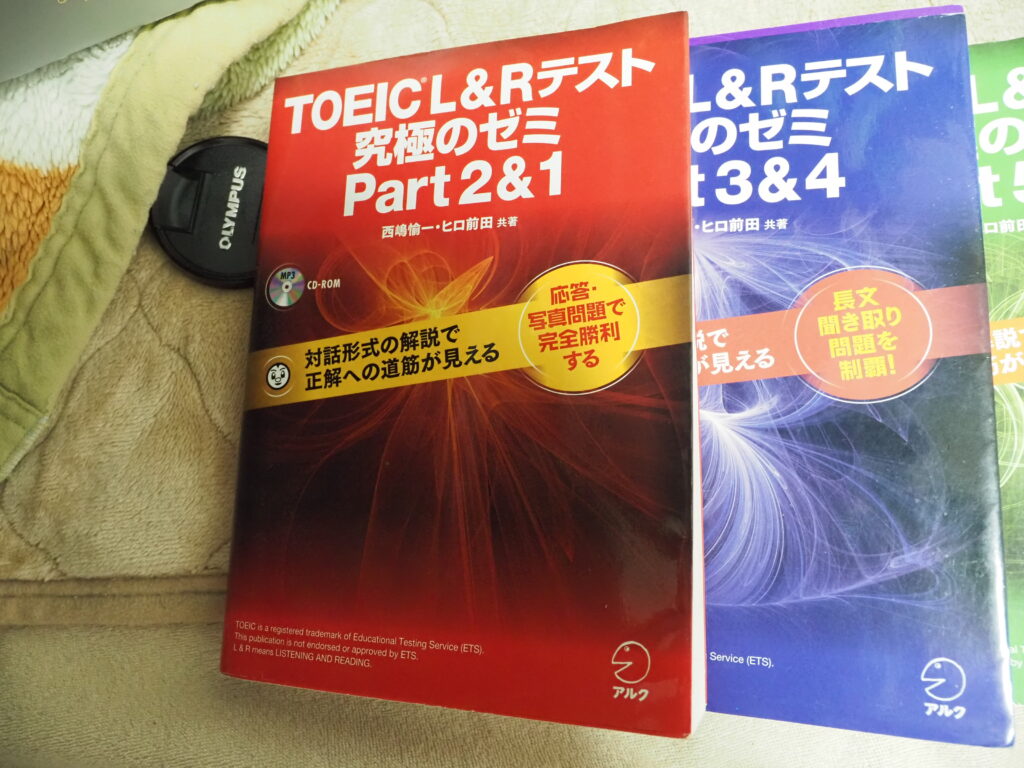
リスニングが苦手だと730ぐらいから点数が鈍化します。
例えば私はリスニングが苦手なものですが、家でできる摸試だと900点は何回も超えています。
本番では900を超えたことがありません。
摸試の方が優しいことや本番には緊張などの要素が入ってくることが影響していると思いますが、特にリスニングは音声が無い1発勝負であるため、立て続けに落としてしまったりするのです。
リスニングは420ぐらいまでは順々に育っていきますが、ここから先は鈍化していくか変わらず伸びていき満点手前ぐらいまで伸びる人に分かれる印象です。
リスニングが高得点で安定できると800点台にはかなり楽に乗れます。L460R340で乗れますからね。
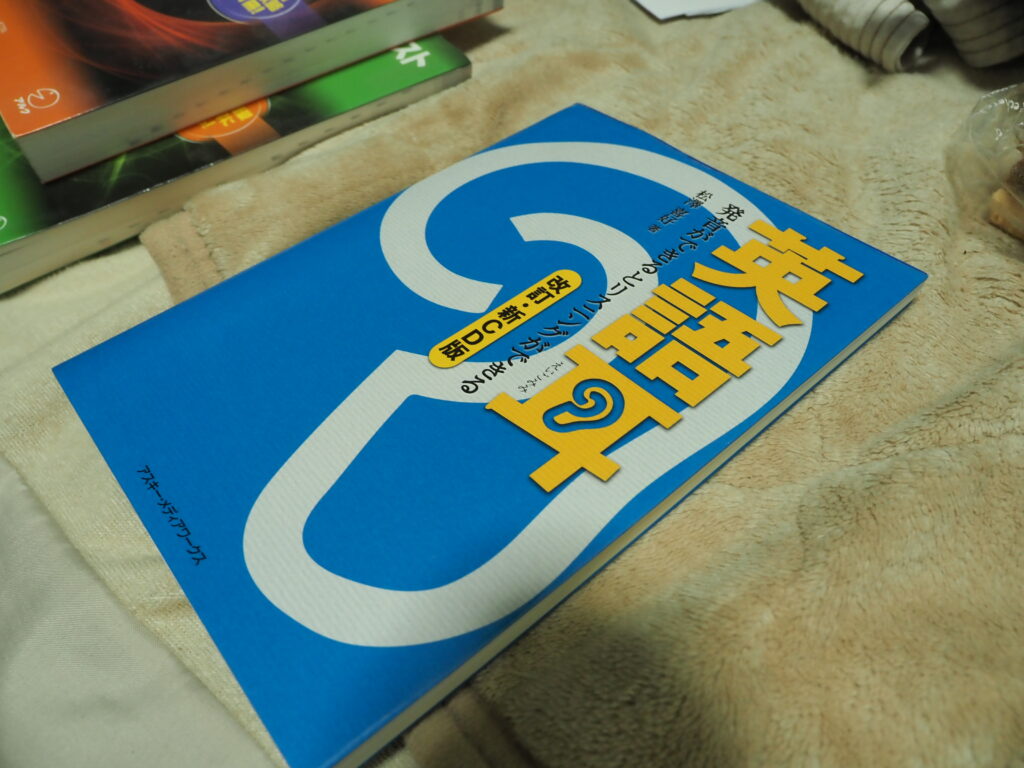
中にはリスニング440リーディング270みたいな偏ったスコアの人もいます。710点でも明らかにリスニングが得意であるということが分かります。
こういう人は成長が早いです。というのもtoeicはリーディングの方が点数を伸ばしにくいからです。
プラトーはリスニングが苦手な人はより早くから感じることになります。私はL420位から停滞しました。
リスニングとリーディングが同じくらいな点数で上がっていく人は受験者の中では珍しい方だと思います。ほとんどの方はリスニング偏重ですよね。
私はほぼ同じで上がってきました。
プラトーには長期的な視点で挑む
toeicはリスニングの点数が重要であると私は考えています。これは問題レベル自体はリーディングよりも簡単なためです。
ただ効果的な策があるわけではありません。
これは収穫逓減の法則というのを理解し、ひたすら時間をかけて対策につぎ込むしかありません。
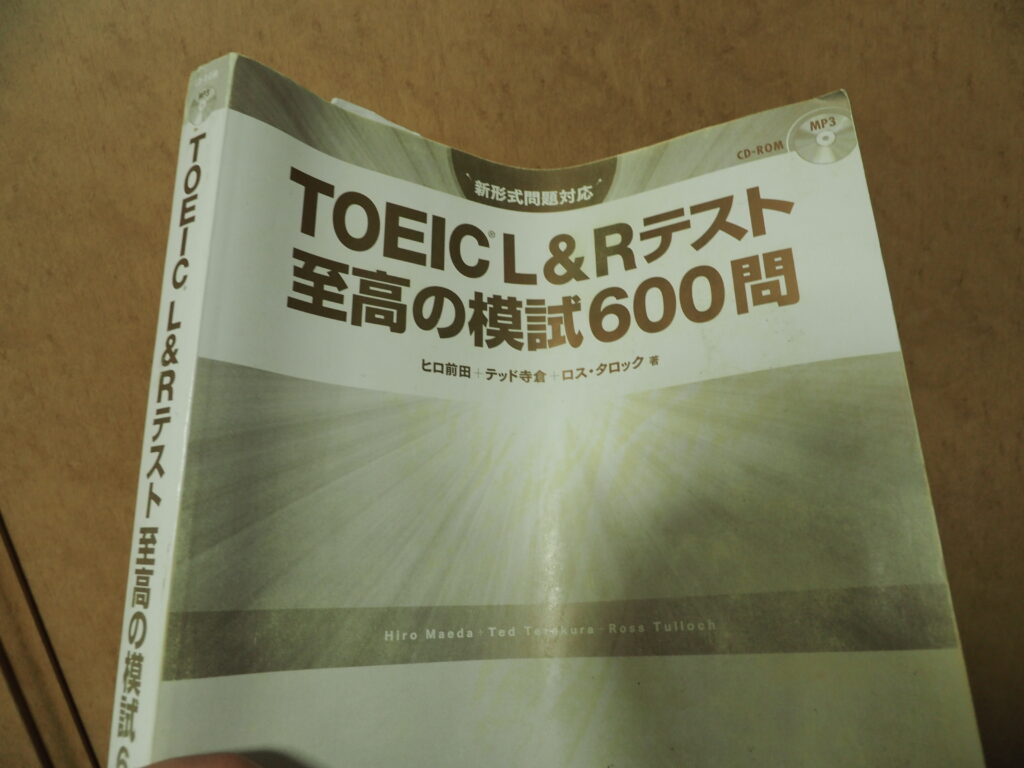
物事というのは時間をつぎ込めばつぎ込むほど成果が出ると考えられていますが、実際はそうではありません。
学習初期と後期では学ぶことの量も吸収する量も全く違いますよね。
例として筋トレで述べると1年目は10kg2年目は5kg、3年目で2kg程度筋肉が付けられると言われています。同じ時間筋トレをしてです。
メーターでいうと7割ラインぐらいまでスムーズに進み、そこから投資する時間に対する伸びが悪くなってきます。
こうした段々とつぎ込む時間に対して効果が悪くなってくることを収穫逓減(しゅうかくていげん)の法則と言います。
つまり点数が8~9割のラインで伸び悩んでしまうというのは必然なのです。
重要なのはプラトーと収穫逓減の法則を理解していつか伸びる日が来ると勉強を続けることです。
400点代前半まで来た方ならその先も問題なく勉強していれば伸びていくはずです。
尚私は475が最高で満点はまだとれていません。
落とし穴は意外に近くにある
収穫逓減の法則はある程度の時間を費やしたところで効果が出てくるため、700点台800点台後半で停滞する方が多いかと思います。
しかし中には500点台や600点台などの点数で停滞するケースがあるかと思います。
この場合は基礎が抜けているという意外な落とし穴があります。
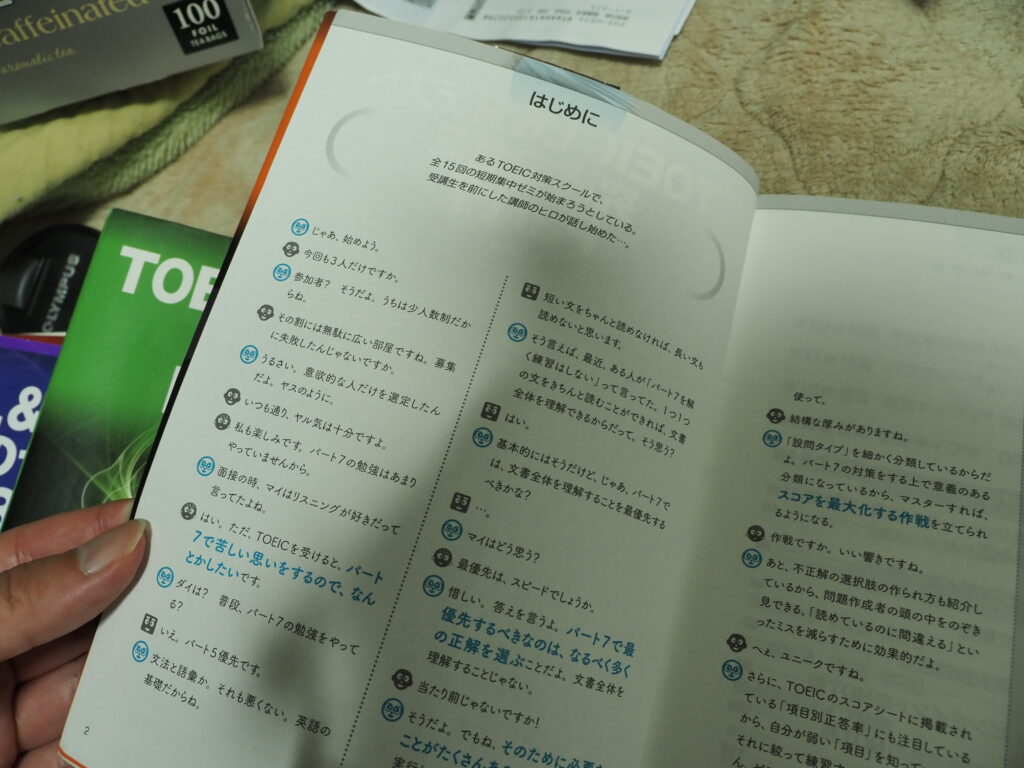
600点台くらいまでは英語の基礎的な部分を理解して、試験慣れと総計400~600時間程度の勉強をすればたどり着けます。(英語力全くの0からの場合)
ところが600手前で停滞するケースというのは意外とあります。
この場合には文法を分かった気になってしまっている自分に気が付く必要があります。
それを矯正してみましょう。
やり方は実に簡単で、精読した教材がきっとありますよね。
その文章に対し、自分が教えてもらっている生徒になった気分で細部を質問してみてください。
duoという単語帳から例文を取るとnatto smells owful but tastes terrificというものがあります。
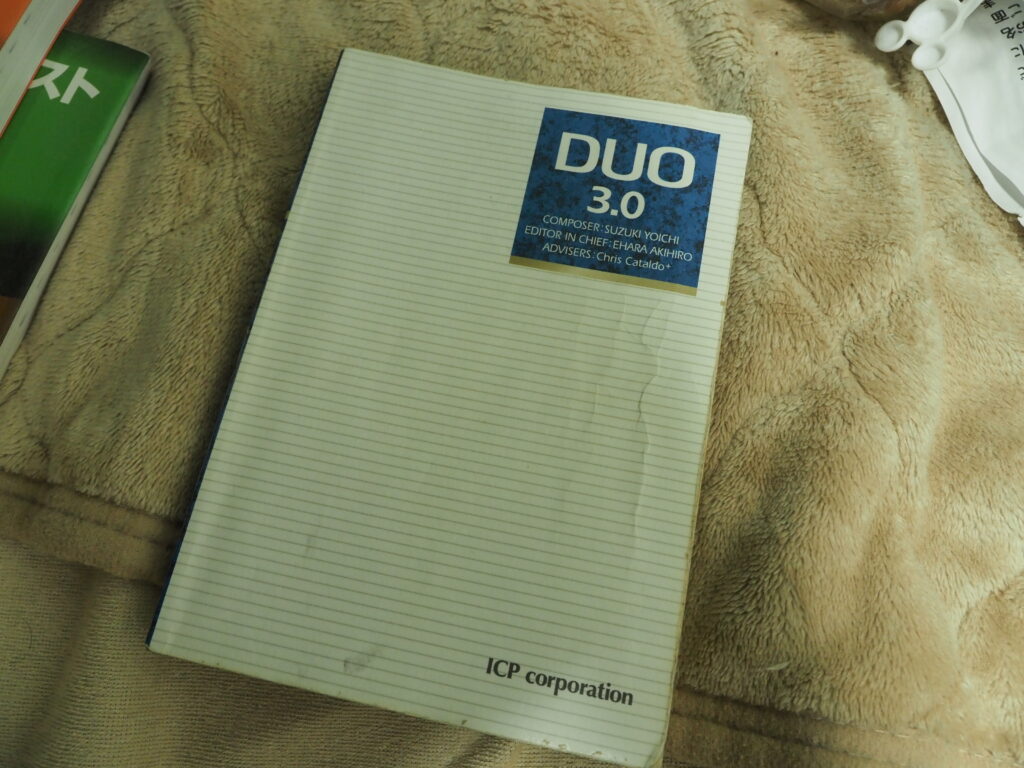
なんで動詞にsがついているんですか?このbutはなんで使われるんですか? butのあとに動詞が続くのは何でですか? nattoに冠詞が無いのは何でですか?
好きなものを目の前にした子供のようにあらゆる疑問を見つけて答えてみると、え?分からないかもという箇所がたくさん見つかります。
それが自分が気が付いていない分かった気になってしまっている箇所です。
私も最近はサボってしまうんですが、精読は他人に突っ込みを入れてやるぐらい細かくやると飛躍的に効果が出ます。
特に基礎的な部分の理解に大きく貢献するので、収穫逓減の法則や750点以上以外でプラトーを感じている場合には試してみてください

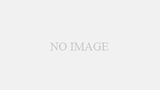

コメント