人に教えることが最大の勉強
英語学習においては継続性が非常に大事です。
もちろん勉強方法もとても大事なのですが、それは勉強をする中で量をこなすと自然と質が上がってきます。
一般的な勉強方法はありふれていますが、勉強の中でよいとされる手法の一つに人に教えるというものがあります。
ここでは教える側に立つというものの中でも一つ踏み込んだ、あなた自身が情報発信側に立ってみると積極的に調べることになるため、情報の定着率が高まりますよ。という話をします。
もしかしらた副業的にお金も稼げるかもしれません。
人に教える方法とは?
今でいうならばこのブログのように英語ブログとして自分の学習内容をコンテンツ化していくことがお手軽な情報発信になります。
こうした媒体を持たなくても英語日記を付けてみるということや、趣味の領域で英文を書いてみるというようなやり方でも構いません。
重要なのは一般の人に見られる形でコンテンツを作ってみることです。例えば高尾山に行ったことを英語で内容を書いてみる。自分で完結するのではなく、人に見られる形で。
いうならば自分がその分野の講師になったつもりで誰かにその内容を説明するような形です。
私はこの英語ブログで色々な法則や効果を絡めたり、自分の英語の過去の学習法を発信していますが、能動的に情報を調べてなるべく読者にもわかりやすく伝えたいというように考えていますのでよく調べます。
その結果、ブログとは関係なく雑談の中でパーキンソンの法則にしろアイゼンハワーマトリクスにしろ有意義なネタとして活用できています。
ジャンルこそ違いますが自然をテーマにしたブログも運用しており、そちらは150万PVぐらいアクセスを集めていますが、記事を書く中で論文や実体験のネタを記事に落とし込む中で改めて生態を知ったり、こんなことしてる生き物だったんだと新たな発見が見つかることも多いです。
やはり人に伝える立場になって深く定着することって多いと思うんですよね。
なぜ教えると定着するのか?
英語学習を行っていると復習をかなりするかと思いますが、自分の定着の悪さにイラついてきますよね。
一方で例えば理系なら研究発表とか人前に立った時の内容って自分でも随分覚えていませんか?
あれは簡易的な人に対して自分の知識を発表する場のようなものです。
つまり人に向けて説明するから適当なことは言えません。だからこそしっかり調べ、突っ込まれないよう細部も見たりするわけです。
自分が生徒なら先生の発言のこの部分にこう突っ込みたいななども考えますよね。
言うなれば連想ゲームのように一つのトピックを複合的な視点から見られるわけです。
このように知識が複数のものと結びつくと定着も良くなります。
英語学習で伸びが悪い人はA=Bと考えてしまいます。すなわち左に単語、右に日本語の意味というような単語帳のような構図です。
しかし単語帳で見た単語が本文中に出ると分からないということがよく起きますよね?
これはA=BもしくはB=Aなのでどちらかの要素からしか連想ができないためです。
逆に連想ゲーム式で記憶すると物忘れしてしまったことが、何かをきっかけに呼び戻されるようにたくさんのキーワードでヒットするようになります。
リンゴという単語を聞いたら赤い丸い果物を想像しますが、春に花を咲かせる、バラ科植物、クビアカツヤカミキリという害虫、人工授粉、ミツバチ。というような感じで多くの要素でリンゴを形成するのが連想ゲーム式です。
apple=リンゴではそれを導き出すのは分かるかどうかですが、春に花を咲かせ、バラ科植物で、クビアカツヤカミキリの脅威にさらされている赤い果物というような形だと赤いリンゴの部分が無くても話の展開が分かり、リンゴもしくはバラ科類の植物の話がされていると分かります。
英語ではこのぼんやり感が大事なのですが、それはこうした語彙の輪郭の部分を押さえておくことが大事なのです。
復習のプロセスをより細分化したものが発信
復習では例えば発音や文構造、単語の意味や音の繋がりなどはよく見ますよね。
でもその文章を人に向けて発信するとしたらどんな風に見た人は思うでしょうか?
あなたの復習したノートの書かれているものを今見たら、自分はどんな突っ込みを加えますか?
情報を発信する場合にはそういうところも見て、ここ突っ込まれそうだなというように一歩踏み込んだ視点を持つことになります。
これはすなわち情報の多角化、つまり先ほどの言葉でいえば連想ゲームのように一つの知識に対して肉付けすることができるのです。
発音についてtやdなどの破裂音が続くと音が続くのはなぜですか?tとrが続くと特殊な音になるのはなぜですか?
単語でフラワーと聞いてお花かと思ったら小麦粉だったことがあったんですけど?(同音異義語)
というような知らないけれども突っ込める要素というのはたくさんあります。
こうしたなぜなにを突き詰めていくというのは非常に学習において効果があり、定着率も高まります。
これを手軽に行い、習慣化するのにブログなどの発信型コンテンツは役に立つのです。
発信することで成長も分かる
こうした発信をすることのメリットはあなた自身が成長を振り返ることができるという点でも優秀です。
あの時こんなことしていたなぁ。そうそうこの時期は発音の疑問に凝っていたなぁ、パート5対策に力を入れていたんだなぁというような自分自身の振り返りと成長を体感しやすいです。
特に600点を目指すならば600点に向かう上でのコンテンツも扱うことになるでしょう。自分の当時の胸中を書いたりもするかもしれません。
すると後々それを見て助かる人や、あの時つらかったなぁというような英語コンテンツ自体が思い出として記録されます。
私の英語ブログはまだまだ記事も少なく浅いものですが、自然ブログの方は3年運用しているとさすがに初期の方は忘れてきており、こんなことあったわ~と鮮明に思い出すことができます。
興味があるものはコンテンツ化する。できればそれでマネタイズを考えていくことがせっかく物事を学ぶ上では効率的だと思いませんか?
英語学習も何にしろブログなどのコンテンツはコンテンツがお金を生み出してくれる媒体です。学習しながらその機会があるならば私は挑戦してみる意義もあると思います。
凄い人かどうかは関係ない
こうしたコンテンツは各領域により難易度が大きく変わる問題はあります。
マイナー程記事は扱いやすいですが、集客はしやすく人気程書く記事には困りませんが集客はしにくいです。
この際、凄い人かどうかは関係がなく、顧客の疑問を解決できるかどうかが重要になります。
SEOやマーケティング的な知識も必要となりますが、逆に言えばブログなどのコンテンツが集客できるならそれらの知識もついてきていることとなります。
英語学習者の中には本ブログのように継続の難しさや挫折してしまうことに悩む人もいれば600点にたどり着けず悩んでいる人などもいます。
逆にビギナーだからこそ気が付ける悩みの部分というのもあるはずです。
そうした顧客の悩みを立場に立って考えるのはペルソナなどと呼ばれますが、コンテンツ作りの際に鍛えられる能力の一つです。
英語学習を例としましたが自分の好きなコンテンツを作り、結果その領域に知識が深まり、マーケティングやSNS戦略の知識もつき、お小遣い程度のお金なら現実的に誰でも狙えますので、英語学習においても挫折の機会を減らしたりすべき理由の動機づけとして一つ考えてみてはいかがでしょうか。


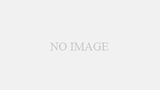
コメント